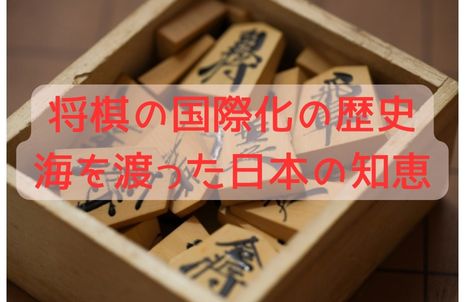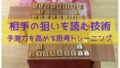将棋は日本が世界に誇る知的遺産の一つです。「日本のチェス」とも呼ばれるこの戦略的ボードゲームは、その独特のルールと深い戦略性で多くの人々を魅了してきました。本記事では、将棋がどのようにして日本という島国を離れ、世界各地へと広がっていったのか、その歴史的な旅路を辿ります。古代インドを起源とするチェス類のゲームが世界各地で独自の進化を遂げる中で、将棋もまた「持ち駒」というユニークなシステムを生み出し、独自の発展を遂げてきました。その魅力はどのように国境を越え、異なる文化の中で受け入れられてきたのでしょうか。初期の海外への伝播から現代のグローバルな広がりまで、将棋の国際化の歴史を探ります。
将棋、その起源と日本の歴史

将棋は単なるゲームではなく、日本の文化と歴史が凝縮された知的遺産です。その起源は遠く古代インドに遡るとされています。
将棋の起源は、古代インドで生まれたチャトランガであるという説が広く受け入れられています。チャトランガは紀元前2000年頃、あるいは3世紀から6世紀頃に誕生し、そこからユーラシア大陸各地に伝播し、各地で独自の発展を遂げました。日本への伝来ルートとしては、中国や朝鮮半島を経由したとする説と、東南アジアを経由したとする説があり、伝来時期も6世紀から11世紀の間と複数の説が存在します。
日本における将棋の最古の記録は、平安時代(1058年~1064年)の『新猿楽記』に見られます。考古学的証拠としては、奈良県の興福寺跡から出土した16点の将棋の駒が最古のもので、1058年の年号が書かれた木簡と共に発見されました。これらの駒はすでに現代の将棋駒と同じ五角形をしており、初期の駒には「玉将」の文字が見られました。
将棋のルールも日本で独自に進化しました。最も特徴的な「持ち駒」のルール、つまり相手から取った駒を自分の駒として再利用できるシステムは、15世紀から16世紀頃(室町時代)に生まれたと考えられています。この独自のルールは、当時の傭兵が捕虜になった際に忠誠を変える慣習に触発されたという説もあります。
現在の将棋(本将棋)のルールは、16世紀に「醉象」の駒が廃止されたことでほぼ確立しました。江戸時代(1603年~1868年)には、将棋は幕府の庇護を受け、「将棋家元制度」が確立。大橋本家、大橋分家、伊藤家の三家が将棋界の中心となり、技術も大きく発展しました。幕府では「御城将棋」が年一度の恒例行事となり、この日が「将棋の日」(11月17日)として現在に至っています。
明治時代(1868年~1912年)になると、新聞に将棋欄が登場し、アマチュアの間でも人気が高まりました。1924年には、プロ棋士の団体である日本将棋連盟が設立され、現代将棋へと繋がっていきます。
初めての海外への伝播 – いつ、どこへ?

将棋が日本を離れ、海外に伝わったのはいつ頃だったのでしょうか。その最初の足跡は意外と古く、隣国の中国にまで遡ります。
記録に残る最も早い将棋の海外への伝播は、明の時代(1368年~1644年)の中国でした。1592年に侯継高によって書かれた『日本風土記』には、倭寇対策のための日本文化研究の一環として、将棋のルールがかなり詳細に記述されています。これは、隣国の中国において、比較的早い時期から将棋が知られていたことを示唆しています。単なるゲームとしてだけでなく、日本の文化を理解するための重要な要素としても認識されていた可能性があります。
西洋で初めて将棋がプレイされた記録としては、1860年に遡ります。この年、日本からアメリカ合衆国への最初の公式使節団(万延元年遣米使節)が訪問した際、使節団のメンバーのうち8人の侍がフィラデルフィア・チェスクラブで将棋を披露しました。佐野鼎と山田馬次郎を含む侍たちは、チェス盤に線を引いて将棋盤に改造し、自前の駒を使って対局を行いました。この出来事は当時の多くのアメリカの新聞で報道され、佐野鼎が将棋のルールを流暢に説明したことが特筆されています。このイベントは、西洋の聴衆に将棋を紹介した最初の記録であり、日本の文化と知性に対する西洋の初めての印象を形成する上で重要な出来事となりました。
その後、1881年にはアントニウス・ファン・デア・リンデによる『チェス史の典拠研究』が出版され、西洋の読者に将棋と中将棋が紹介されました。リンデの著作は、ヨーロッパの学者やチェス愛好家に対して将棋の情報を広め、初期の学術的な関心を高める上で重要な役割を果たしました。
世界に広がる将棋の輪 – 現在の普及状況

現代では、将棋は日本国外でも徐々に知られるようになり、世界各地に愛好家のコミュニティが形成されています。その広がりと現状について見てみましょう。
現在、将棋はヨーロッパ、アジア、オセアニア、北米、南米、アフリカなど、様々な国や地域に広がりを見せています。各地に将棋連盟や団体、クラブが存在し、着実にファンを増やしています。
ヨーロッパでは、1985年に設立されたヨーロッパ将棋連盟(FESA)が、将棋の普及と組織化に中心的な役割を果たしています。同じく1985年には、ヨーロッパ将棋選手権(ESC)が初めて開催され、ヨーロッパの将棋プレイヤーにとって重要な競技の舞台となっています。
しかしながら、これらの努力にもかかわらず、日本国外における将棋の人気は、チェスや象棋といった他の戦略ゲームと比較すると、依然として低い水準にあるのが現状です。将棋が持つ独特の魅力や奥深さが、まだ十分に世界に浸透しているとは言えません。それでも、着実に普及活動は続けられており、近年ではインターネットの普及により、オンライン対局を通じて将棋の魅力に触れる海外の人々も増えています。
国際化の立役者たち – 海外で活躍する棋士と普及貢献者

将棋の国際化の道のりには、熱心な個人の献身的な努力が不可欠でした。彼らの活動が、異文化の壁を越えて将棋を広める原動力となっています。
将棋の国際化に大きく貢献している人物として、カロリーナ・ステチェンスカが挙げられます。彼女は、2017年に日本人以外で初めて日本将棋連盟からプロ棋士の資格を授与されたポーランド出身の女性です。日本の漫画を通じて将棋を知り、オンライン対局で腕を磨いた彼女は、「ヨーロッパにおける将棋の国際化」をテーマに修士論文を執筆しました。
現在も、自身のウェブサイトや「International Shogi Magazine」を通じて、英語で将棋のルールを紹介するなど、世界的な普及活動に積極的に取り組んでいます。2018年には、ロサンゼルスで開催された国際大会にも参加し、海外での将棋普及に貢献しました。彼女の存在は、文化の壁を越えて将棋の魅力を世界に伝える象徴的な出来事と言えるでしょう。
また、1975年にイギリスで将棋協会(TSA)を設立し、雑誌「SHOGI」を創刊したジョージ・ホッジスも、ヨーロッパにおける将棋普及の初期の重要な人物です。彼のような初期の熱心な提唱者たちの活動が、海外における将棋コミュニティの基盤を築きました。
こうした個人の情熱と努力が、将棋の国際化を支える大きな力となっています。彼らは自らの体験を通じて、将棋の魅力を異なる文化背景を持つ人々に伝え、新たな将棋愛好家を生み出す架け橋となっているのです。
異文化の中での受容 – ルールと普及の課題

将棋が海外で広まる過程では、様々な文化的・言語的障壁が立ちはだかります。これらの課題とその解決に向けた取り組みは、将棋の国際化において重要な側面です。
将棋の国際的な普及には、いくつかの課題が存在します。その一つが、伝統的な将棋駒に書かれている漢字の存在です。多くの非日本語話者にとって、漢字を理解することは大きなハードルとなります。また、将棋独特のルールである「持ち駒」のシステムは、ゲームに複雑さと奥深さを与える一方で、初心者にとっては理解が難しい場合があります。
日本語以外の言語での学習教材が不足していることも、普及の妨げとなっています。一部の西洋文化圏では、将棋がニッチなゲーム、あるいは「オタク」文化のゲームと見なされる傾向もあります。さらに、チェスのような、より確立された戦略ゲームとの競争も避けられません。
対局時間が他のボードゲームと比較して長くなる場合があることや、ゲームに対する文化的な認識の違い(趣味としての側面と文化的遺産としての側面)も、普及における課題と言えるでしょう。
これらの課題に対して、様々な取り組みや工夫が行われています。漢字の代わりに、アイコンや英語の表記を用いた「国際駒」や「西洋化された駒」の開発と使用は、初心者にとって将棋を学びやすくする可能性があります。伝統的な美学を重視する意見もありますが、入門の段階では有効な手段となり得ます。
また、英語話者向けに将棋の棋譜をチェスの記譜法で記録する試みも行われています。英語をはじめとする多言語での学習教材の作成も、普及には不可欠です。将棋を単なる文化的遺産としてではなく、魅力的で知的なゲームとして宣伝することも重要です。
これらの取り組みを通じて、将棋の本質を損なうことなく、より多くの人々に親しみやすい形で提供することが、国際化の鍵となるでしょう。
国際的な競技の舞台 – 海外の将棋大会とイベント

将棋の国際化において、競技としての側面も重要です。世界各地で開催される大会やイベントは、将棋愛好家が集い、交流する貴重な機会となっています。
ヨーロッパ将棋選手権(ESC)は、海外における主要な国際将棋大会の一つです。1985年に始まったこの大会は、ヨーロッパの将棋プレイヤーにとって重要な競技の舞台となっています。
その他にも、カロリーナ・ステチェンスカが参加した2018年のロサンゼルスでの大会など、世界各地で様々な国際将棋大会やイベントが開催されています。2023年には、アメリカが初めてワールド将棋リーグで優勝するという出来事もありました。
しかしながら、これらの国際的な競技の規模や頻度は、チェスの大会と比較すると、まだ小さいと言わざるを得ません。それでも、こうした大会やイベントは、将棋の国際的な認知度を高め、海外の将棋コミュニティを活性化させる上で重要な役割を果たしています。
将来的には、より大規模で頻繁な国際大会の開催や、メディア露出の増加などを通じて、競技としての将棋の国際的なプレゼンスが高まることが期待されます。また、プロ棋士と海外のアマチュアプレイヤーの交流機会を増やすことも、将棋の魅力を世界に伝える上で効果的でしょう。
オンライン対局の力 – グローバルな普及への貢献
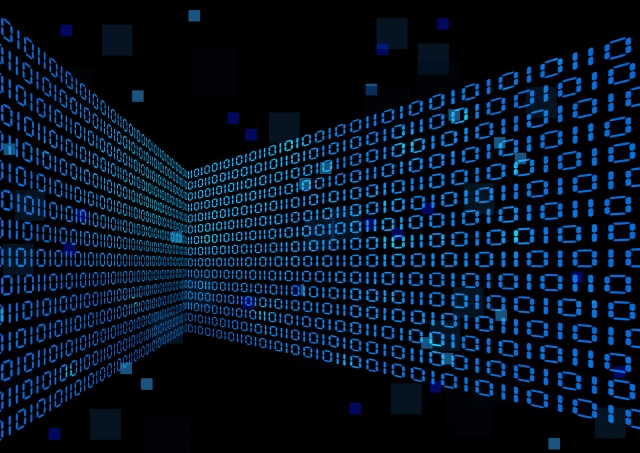
インターネットの普及は、将棋の国際化に革命をもたらしました。地理的な障壁を取り払い、世界中のプレイヤーをつなぐオンラインプラットフォームの役割は計り知れません。
オンラインの将棋プラットフォームやアプリは、世界中のプレイヤーを結びつけ、将棋の国際的な普及に大きな役割を果たしています。特に81Dojo.comのようなプラットフォームは、海外のプレイヤーが対戦相手を見つけ、学習し、オンライン大会に参加するための重要なツールとなっています。
オンラインプラットフォームは、地理的な障壁を克服し、どこにいても将棋を学び、プレイすることを容易にしました。カロリーナ・ステチェンスカのように、オンライン対局を通じて腕を磨き、プロへの道を切り開いた例もあります。
ただし、一部のプラットフォームでは、ウェブサイトのデザインや非日本語話者にとってのアクセシビリティに課題が残されている可能性もあります。今後、より多言語対応したユーザーフレンドリーなプラットフォームの発展が期待されます。
将棋AIの発展も、オンライン将棋の世界に新たな可能性をもたらしています。初心者から上級者まで、自分のレベルに合った対戦相手としてAIを活用できることで、学習の機会が広がっています。
オンライン対局の環境が整備され、より多くの人々が手軽に将棋を楽しめるようになることで、将棋の国際化はさらに加速するでしょう。物理的な距離や言語の壁を超えて、共通の知的楽しみとしての将棋の魅力が、世界中に広がっていくことが期待されます。
まとめ

将棋の国際化の歴史は、その起源から現代のグローバルな広がりまで、長く興味深い道のりを辿ってきました。日本で育まれた知的ゲームが、どのようにして海を越え、異なる文化の中で受け入れられてきたのか、その過程には多くの挑戦と成果がありました。
明の時代の中国での言及や、1860年のフィラデルフィアでのデモンストレーションといった初期の出来事は、将棋が海を渡り始めた重要な一歩でした。そして現在、ヨーロッパ将棋連盟の設立やヨーロッパ将棋選手権の開催、カロリーナ・ステチェンスカのようなプロ棋士の誕生、オンライン対局プラットフォームの発展など、様々な取り組みが将棋の国際的な普及を支えています。
将棋は、豊かな歴史、複雑なルール(特に持ち駒)、そして奥深い戦略性という独自の魅力を持っています。漢字の理解や文化的な違いなど、国際化にはいくつかの課題もありますが、「国際駒」の開発や多言語の学習教材の作成など、これらの障壁を乗り越えるための努力も続けられています。
今後、「海を渡った日本の知恵」である将棋が、より多くの人々に親しまれ、世界中でその魅力が理解されるようになることが期待されます。伝統と革新を両立させながら、将棋は国境を越えて人々の心を結びつける知的な架け橋として、その役割を果たし続けるでしょう。私たち一人ひとりも、将棋の国際化の一翼を担い、この素晴らしい日本の知恵を世界に広げていく担い手となれることを願っています。