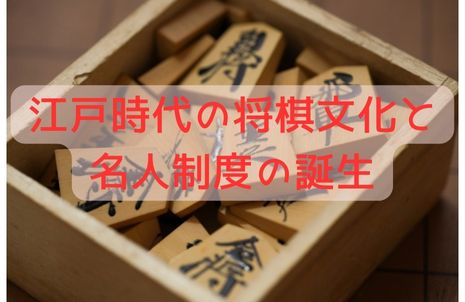江戸時代、将棋は単なる遊戯を超え、幕府に公認された重要な文化として日本社会に根付きました。徳川家による庇護のもと、将棋所という組織が設立され、名人制度や御城将棋といった伝統が生まれました。この時代に確立された将棋の基盤は、現代の将棋界にも大きな影響を与えています。ここでは、江戸時代における将棋の発展と、その社会的・文化的背景について探っていきましょう。
徳川幕府と将棋 – 御城将棋の成立

江戸時代初期、徳川幕府は将棋を特別な技芸として認め、その保護に乗り出しました。当初は囲碁と一緒に「碁将棋所」として扱われていましたが、1612年(慶長17年)に大橋宗桂に俸禄が与えられ、将棋は独立した地位を獲得します。これにより、将棋所が正式に設立され、将棋は幕府公認の文化として認められるようになりました。
将棋所の主な役割は将棋界の統括と、将軍御前で行われる「御城将棋」の執行でした。御城将棋は当初は不定期でしたが、1716年(享保元年)に徳川吉宗の時代になると、毎年旧暦11月17日に行われる公式行事として制度化されました。この日付は現在でも「将棋の日」として引き継がれています。
興味深いことに、御城将棋は表向きは将軍の前で技を披露する場でしたが、実際には将軍が観戦することはほとんどなく、老中が短時間見学する程度だったようです。また、当初は対局をその日のうちに終わらせる習わしでしたが、次第に事前に指しておいた手順を再現する儀式へと変化していきました。こうした変遷からは、将棋が幕府の公式行事として重視される一方で、実用性よりも形式や秩序が優先される側面もあったことがうかがえます。
将棋大橋家の成立と役割
江戸時代の将棋界において中心的役割を果たしたのが、大橋家でした。初代大橋宗桂は将棋界の基礎を築いた人物として知られており、1612年に将棋所の頭に任命されました。大橋本家は、大橋分家、伊藤家とともに江戸時代の将棋における三家となり、この三家が将棋所を世襲していきました。
特に二代大橋宗古は将棋のルール整備に貢献し、「棋道治式三カ条」と呼ばれる禁手(二歩、行き場のない駒打ち、打ち歩詰め)を明文化しました。また、千日手の規定や段位と駒落ちの関係に関するルールも定め、将棋界の秩序を確立しました。
寛文年間(1661-1673年)には、幕府の命により大橋家は京都から江戸へ移住し、幕府の文化的活動により深く関わるようになります。1670年には江戸に屋敷を与えられ、その地位は確固たるものとなりました。大橋家の江戸移住は、幕府が文化の中心を江戸に集約し、優れた技能を持つ者を自らの影響下に置こうとした政策の一環だったと考えられます。
名人制度の誕生と発展
江戸時代の将棋界において、最も権威ある地位が名人でした。初代名人となった大橋宗桂は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕え、その将棋の腕前を披露したことで知られています。1612年に江戸幕府から50石5人扶持の俸禄を与えられ、将棋所の頭に任命されたことが、正式な名人位の始まりとされています。
宗桂は1602年に現存する最古の詰将棋集『象戯作物』を出版し、後陽成天皇に献上しました。また、1616年には幕府にも作品集を献上し、これが後の名人が倣う先例となりました。彼と本因坊算砂との将棋の対局は、現存する最古の棋譜の一つとしても知られています。
江戸時代における名人の地位は世襲制であり、大橋本家、大橋分家、伊藤家の三家の当主がその地位を継承しました。通常、これらの三家の中で最も実力のある者が名人とされ、将棋所の地位を兼ねました。この時代の名人は九段の棋力を持つ者とされ、八段は「準名人」、七段は「上手」と呼ばれていました。
しかし、江戸時代後期になると、家元制度の枠組みを超えて在野の強豪棋士が現れるようになります。大橋柳雪や天野宗歩はその代表的存在で、特に天野宗歩はその圧倒的な実力で将棋界に大きな影響を与えました。
世襲制による名人制度は江戸幕府の崩壊とともに終焉を迎え、明治時代には推薦制へと移行します。そして1935年、13世名人の関根金次郎の引退を契機に、実力によって名人を決める名人戦が創設され、現代の名人制度の礎が築かれました。
城下将棋の文化と広がり
江戸時代、将棋は全国各地で様々な形で愛されていました。京都は公家の存在から将棋が盛んであり、宗桂のような町衆や僧侶、武士などの強豪が現れました。将棋の普及の中心となったのは武士で、参勤交代によって国元に帰った武士たちが地方に将棋を広めていきました。
将棋好きの城主がいる藩では特に将棋が盛んであり、越中藩主松平長門守や加賀藩主前田重教などが将棋を奨励しました。一方で、多くの藩では将棋はあまり奨励されず、賭け事として禁止されることもありました。このように、将棋に対する姿勢は藩によって異なっていました。
徳川将軍家も将棋を保護し、家康自身も将棋に親しんでいたと言われています。特に八代将軍徳川吉宗は将棋を好み、詰将棋集を編集したことでも知られています。将棋を好む大名は自身の領内でも将棋の普及を奨励し、優秀な棋士を育成しました。
江戸時代後期になると、将棋は庶民の間でも広く親しまれるようになり、各地の城下町には将棋サロンのような場所が現れ、人々が気軽に将棋を楽しめる環境が整いました。1831年には江戸で初代大橋宗桂の200年忌を記念する将棋大会が開催され、有段者を含む80組以上が参加するなど、将棋の裾野は大きく広がっていきました。
江戸時代の将棋書と普及活動
江戸時代初期から、将棋に関する書籍が次々と出版されました。初代大橋宗桂の『象戯作物』(1602年)を皮切りに、二代大橋宗古の『象戯図式』(1635年)、初代伊藤宗看の『象戯図式』(1649年)など、詰将棋集が多く刊行されました。特に伊藤宗看は今日にも通じる詰将棋のスタイルを確立し、「近代詰将棋の父」と呼ばれています。
江戸時代中期以降には、序盤の戦略や戦法に特化した定跡書も登場します。大橋宗英の『将棋歩式』、福島順喜の『将棋絹篩』、天野宗歩の『将棋精選』は「三大定跡書」として知られ、特に『将棋精選』に掲載された戦法の一部は現代のプロ棋戦でも用いられています。この頃には相掛かりや横歩取りといった戦型について、詳細な手順が研究されていました。
元禄時代(1688-1704年)以降になると、家元以外の民間棋士による詰将棋集も出版されるようになり、伊野辺看斎や添田宗太夫といった人物が、テーマ性のある斬新な作品を発表しました。こうした詰将棋集の普及は、将棋の愛好家層の拡大に大きく貢献し、単なる対局だけでなく、詰将棋という知的パズルを楽しむ文化を広めました。
江戸の将棋茶屋と町人文化

江戸時代、将棋は庶民の間でも広く楽しまれるようになり、「将棋茶屋」と呼ばれる、人々が将棋を指して過ごせる場所が登場しました。これらの将棋茶屋は、都市に住む将棋愛好家たちの社交場としての役割を果たし、様々な身分の人々が集い、将棋を通じて交流する場となりました。
将棋茶屋の出現は、将棋が一部の特権階級の遊戯から、庶民の日常生活に根付いた娯楽へと変化したことを示す象徴的な出来事です。江戸の活気ある都市文化の中で、将棋茶屋は手軽に楽しめる娯楽の場として、重要な役割を果たしました。
また、江戸時代には名人位は三家の当主が世襲しましたが、町人の中からも優れた棋士が現れました。特に天野宗歩は、その実力と人気により、将棋家からも無視できない存在となり、御城将棋にも出場するほどでした。町人の中から家元に匹敵するほどの力量を持つ棋士が現れたことは、江戸時代の将棋界において、実力主義的な側面も存在していたことを示唆しています。
幕末から明治への変遷
幕末期にも三つの将棋家から優れた名人が輩出されましたが、政治的・社会的な混乱は将棋界にも影響を与えました。1864年(元治元年)に最後の御城将棋が行われたことは、当時の社会情勢の不安定さを反映しています。
1868年の明治維新は徳川幕府の終焉をもたらし、将棋家に対する庇護も失われました。世襲制度は公式な後ろ盾を失い、伝統的な将棋界は危機に瀕します。将棋家は後継者を失い、家元制度は1893年の11世伊藤宗印の死をもって事実上終焉を迎えました。
しかし、俸禄を失った将棋指したちは、庶民に向けて将棋教室を開いたり、書籍や雑誌を出版したりすることで、将棋の普及に努めました。明治後期に始まった新聞の将棋欄も、将棋の大衆化に大きく貢献しました。
明治維新は日本の社会構造を大きく変革し、それは将棋界も例外ではありませんでした。幕府の庇護を失ったことは伝統的な将棋界にとって大きな試練となりましたが、同時に、将棋をより広い層の人々に普及させるための新たな動きが生まれた時期でもありました。江戸時代に培われた将棋の伝統と知識は、こうして近代将棋へと受け継がれていったのです。
まとめ

江戸時代は将棋の発展にとって極めて重要な時期でした。徳川幕府による保護のもと、将棋所が設立され、名人制度が確立され、御城将棋という伝統行事が生まれました。大橋家を中心とする三家による世襲制は将棋の伝統を守り、数多くの将棋書の出版は技術の向上と普及に貢献しました。
同時に、将棋茶屋の登場や町人棋士の活躍は、将棋が庶民文化として広く根付いていったことを示しています。江戸時代に確立された将棋の基盤は、明治維新という大きな社会変革を経ても失われることなく、実力制への移行など新たな形で発展しながら、現代の将棋文化へと受け継がれていきました。
江戸時代における将棋の発展は、単なる遊戯の歴史ではなく、日本の文化や社会の変遷と密接に結びついた物語です。徳川家による文化保護政策、武士による文化の地方への伝播、町人文化の発展、そして明治維新による社会変革といった歴史の流れの中で、将棋はその姿を変えながらも、日本人に愛され続けてきました。その豊かな歴史と伝統は、現代の将棋界にも脈々と息づいています。