近年、将棋界はかつてない盛り上がりを見せています。多くの将棋ファンが「将棋センス」について考えることがあるでしょう。「センスがいい人はこう指す」「センスがないから上達しない」というフレーズをよく耳にします。しかし、この「将棋センス」とは実際何なのでしょうか?また、それは生まれつきの才能なのか、それとも鍛えられるものなのでしょうか?この記事では、将棋センスの正体とその鍛え方について深掘りしていきます。
「将棋センス」とは何か – その実体を探る

将棋センスとは一言で言えば「局面を見た瞬間に良い手が直感的に分かる能力」です。しかし、その背後には複雑な認知プロセスと経験の蓄積があります。センスの本質を理解することが、その鍛え方を知る第一歩となります。
センスの本質:直感と論理の融合
将棋界最高峰の棋士は、将棋のセンスについてこう語っています。
「ぱっと局面を見たときに、いい手が浮かぶかどうか、駄目な手が瞬間的に分かるかどうかというセンスの要素はあります。持って生まれたものでそれができる人もたぶんいると思います。積み重ねの中で力を磨く面もあります」
つまり、将棋センスには:
- 瞬間的な良手の認識能力
- 明らかな悪手を即座に排除する能力
- 先天的な要素と後天的な積み重ねの両面
が含まれているのです。
形勢判断力としてのセンス
将棋では「形勢判断」が非常に重要です。形勢判断には以下の4つの基準があります。
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 玉の堅さ | どちらの玉がより堅く守られているか |
| 駒の損得 | どちらがより有利な駒交換をしているか |
| 駒の働き | 各駒がどれだけ効果的に機能しているか |
| 手番 | 次に指すのはどちらか |
これらを瞬時に判断できる能力も、将棋センスの重要な一部です。形勢判断の優れた棋士は、一見複雑な局面でも正確に優劣を見抜き、最適な手を選択できます。
感覚と言語化の関係
注目すべきは将棋センスと言語化能力の関係です。「感覚で将棋を捉えているから上達しない」という指摘があるように、なぜその手が良いのか、悪いのかを言葉で説明できることが、本当のセンスを磨くために重要なのです。
センスの基礎となる能力と素質
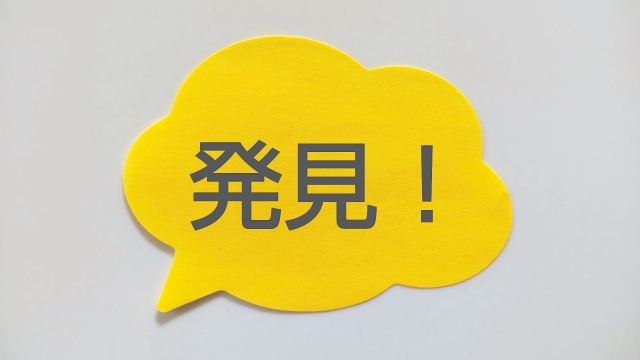
将棋センスは複数の基礎能力から構成されています。これらの能力を認識し、個別に強化することで、総合的なセンスを向上させることができます。
駒の動きを直感的に把握する能力
将棋センスの基礎となるのは、まず駒の動きを直感的に把握できる能力です。初心者が「銀」と「金」の動きをよく混同するように、駒の動きを瞬時に理解し把握することは、実は高度な認知能力を必要とします。
- 利きの把握: プロ棋士は複雑な局面でも各駒の利きを瞬時に把握
- 駒の働きの瞬時理解: 各駒がどの方向にどれだけ効果を発揮しているか
- 駒の連携の直感的理解: 複数の駒がどのように協力しているか
これらの能力は天賦の才というよりも、膨大な経験と訓練の結果です。
局面の評価能力
局面を正確に評価する能力も重要です。これには「大局観」と呼ばれる、局面全体を見渡す視点が必要となります。経験豊富な棋士は、「駒の損得」「玉の安全度」「駒の働き」「手番」の4つの要素を常に意識し、局面全体のバランスを把握する感覚を養っています。
パターン認識能力
将棋には「良い形」「悪い形」といったパターンが無数にあります。これらのパターンを認識し、記憶する能力も将棋センスの重要な要素です。
「詰将棋」を数多く解いて様々なパターンを体に染み込ませたり棋譜並べなどの訓練によってパターン認識能力を磨くのも有効です。
「駒感覚」を養うトレーニング法

駒感覚は将棋センスの中核をなす能力です。駒の動きや連携を直感的に理解することで、複雑な局面でも正確な判断ができるようになります。効果的なトレーニング法を取り入れて、駒感覚を磨いていきましょう。
詰将棋で磨く駒の感覚
駒感覚を養うための最も効果的な方法の一つが「詰将棋」です。
詰将棋のメリット:
- 駒の動きや連携を直感的に理解できる
- 読み抜けが少なくなる
- 頭の中で駒を動かすスキルが向上する
特に簡単な詰将棋を多く解くことで、効率よく駒感覚を磨くことができます。
「成り駒将棋」で序盤感覚を養う
子ども向けの将棋教室で考案された「成り駒将棋」は、序盤の駒の連携感覚を養うのに効果的です。
成り駒将棋のルール:
- 次の一手で取られない「成り駒」を作れば勝ち
- シンプルなルールだが深い戦略性がある
- 駒の連携や配置の感覚が自然と身につく
このゲームでは、一手一手の判断が勝敗に直結するため、慎重な指し手を意識するようになります。
「駒の利き」を可視化する訓練
駒の利きを直感的に理解するための訓練方法として、局面の各マスに「利いている駒」を実際に書き出すという方法があります。
可視化訓練の手順:
- ある局面を設定する
- 各マスに利いている駒を書き出す
- 複数の駒が利いているマスに注目する
- 利きの薄いマスを把握する
「駒の動きを覚えさせるには、盤面にと金をたくさん用意し、それぞれの駒の動きに応じてと金を置いてもらう形にしています」という工夫も、駒の利きの感覚を養うのに役立ちます。
形勢感覚を磨く具体的方法

形勢感覚とは、局面の優劣を正確に判断する能力です。この感覚を磨くことで、どの局面でも最適な戦略を選択できるようになります。形勢感覚を効率的に向上させる方法を見ていきましょう。
4つの基準による形勢判断の訓練
形勢感覚を磨くためには、対局中に常に4つの基準を意識することが重要です。
自問自答のポイント:
- 「自分は駒得しているか?」
- 「玉の安全は保たれているか?」
- 「駒は十分に働いているか?」
- 「手番が自分にあるか?」
このように常に自問自答することで、形勢判断の精度が高まります。
局面ごとの重点チェック項目
対局の各段階で重視すべき形勢判断の項目は異なります。
| 対局段階 | 重視すべき項目 |
|---|---|
| 序盤 | (1)玉の堅さ (3)駒の働き |
| 中盤 | (2)駒の損得 (3)駒の働き |
| 終盤 | (1)玉の堅さ (4)手番 |
このように、局面の進行に応じて注目点を変えることで、より正確な形勢判断ができるようになります。
良手と悪手の比較分析
形勢感覚を磨くには、良手と悪手を比較する訓練も効果的です。
比較分析の方法:
- 「次の一手」形式の問題を解く
- なぜその手が良いのか、悪いのかを論理的に考える
- 異なる手の結果を比較検討する
「野間俊克氏の『将棋・本筋の考え方』は、『本筋』とされる良い手をあえて悪い手と比較しながら解説するユニークな二択問題形式の本です」というように、良手と悪手を明確に比較することで、将棋の理論的な理解が深まります。
実戦感覚を高める対局アプローチ

実戦感覚は、実際の対局で培われる総合的な判断力です。単に対局数を増やすだけでなく、質の高い対局体験と振り返りが重要です。実戦感覚を効果的に高めるアプローチを紹介します。
実戦から学ぶための振り返り方
実戦感覚を高めるには、ただ対局を重ねるだけでなく、対局後の振り返りが非常に重要です。
効果的な振り返りのポイント:
- 自分の指した手や思考プロセスを詳細に言語化する
- ミスや判断の誤りについて「なぜその手を指したのか」を分析する
- 「どこで悪い判断があったのか」を徹底的に追求する
「対局の反省をきっちりすること」が最も良い上達法だという意見があるように、対局後の分析が実戦感覚を高める鍵となります。
棋譜並べによる実戦感覚の獲得
プロの棋譜を並べることも、実戦感覚を高める効果的な方法です。
棋譜並べの効果:
- 一局の流れがつかめる
- 符号が読めるようになる
- 攻めや守りの手筋が身に付く
- 指し手の幅が広がる
- 勝ち切り方、逆転の仕方が分かる
「実戦で指された、しっかり勝ち切る指し手や逆転の狙いを秘めた指し手を自分自身で並べることで、終盤の感覚が研ぎ澄まされていく」という効果が期待できます。
「次の一手」問題による実戦判断力の向上
「次の一手」形式の問題を解くことも、実戦での判断力を養うのに役立ちます。実戦的な局面から最善手を考える訓練を積むことで、実際の対局での判断力が向上します。
「『次の1手』という問題形式で、手筋や局面の読みを学ぶと、実戦での判断力が向上します」という指摘があるように、実戦的な判断力を伸ばすには、具体的な局面での思考訓練が欠かせません。
センスを磨くための日常習慣

将棋センスを効果的に磨くには、日々の習慣が鍵となります。継続的な学習と適切な休息のバランスを取りながら、将棋との関わり方を工夫することで、着実にセンスを向上させることができます。
毎日の短時間学習の効果
将棋センスを磨くには、毎日の短時間学習が効果的です。「1日1時間将棋に触れ、3局は指しましょう」というアドバイスがあるように、習慣化することが重要です。
日常に組み込むアイデア:
- 朝のトイレで詰将棋
- 通学中に次の1手
- ランチ後の対局
- 寝る前の定跡書の読書
このように日々のルーチンに将棋を組み込むことで、無理なく将棋に触れる時間を確保できます。
プロ棋士に学ぶ習慣形成
プロ棋士の習慣から学ぶこともできます。ある高名なプロ棋士のアプローチは示唆に富んでいます。
「休むときは休み、集中するときは集中するようなメリハリは大事」 「頭の中でも考えられるので考えたいと思ったときにそうしています。これぐらいの量を考えなくてはいけないという感覚は持っていません」
このように、柔軟なアプローチと適切な休息も、センスを磨くための重要な要素です。
定跡と基本手筋の日常的反復
定跡や基本手筋を日常的に反復することも重要です。
効果的な反復のポイント:
- 「定跡は質より量」という考え方
- 多くのパターンを体に染み込ませる
- 特定の戦法に絞って集中的に学ぶ
「戦法を固定して徹底的に定跡を研究すること」が初段達成への近道とされるように、効率的にセンスを磨くことができます。
独自のセンスを開花させる長期的アプローチ
真の将棋センスとは、単に教科書的な知識を身につけることではなく、自分だけの独自の感性を育てることにあります。長期的な視点で自分のスタイルを確立し、個性的なセンスを開花させる方法を考えていきましょう。
自己分析による強みと弱みの把握
独自のセンスを開花させるには、まず自己分析によって自分の強みと弱みを把握することが大切です。
自己分析のステップ:
- 自分の得意不得意を洗い出す
- 強みを伸ばす方法を考える
- 弱みを補う対策を立てる
- 自分だけの個性を見つける
「短所と長所は表裏一体です。…自分の何が長所なんだろう、そう考えることが自分だけの『才能』を見つけ出すヒントになります」という指摘があるように、弱点を知ることが独自のセンスを開花させる第一歩となります。
独自の戦法や手筋の開発
独自のセンスを開花させるには、誰も予測しない妙手や革新的な新手を模索する姿勢が重要です。常識にとらわれない発想が独自のセンスを形成します。
長期的視点での実力向上計画
独自のセンスを開花させるには、長期的な視点での実力向上計画も欠かせません。
効果的なロードマップ作成:
- 初段達成までの目標を設定
- 序盤・中盤・終盤に分けた勉強法の優先順位を明確化
- 「序盤→終盤→中盤+実践」の順で学習を進める
- 自分の強みと弱みに応じた対策を行う
このような計画的なアプローチにより、独自のセンスが徐々に開花していきます。
まとめ

将棋センスとは、先天的な才能だけでなく、適切な訓練と日々の研鑽によって磨かれる総合的な能力です。この記事で紹介した方法を実践することで、あなた自身の将棋センスを着実に向上させることができるでしょう。
将棋センス向上の核となるポイント:
- 駒感覚、形勢感覚、実戦感覚を総合的に高める
- 日常的な習慣の中に将棋を取り入れる
- 自分の強みと弱みを理解し、独自のスタイルを確立する
- 継続的な努力こそがセンスを磨く鍵となる
永世七冠が「苦しまないで努力を続けられるということが、何より大事な才能」と語るように、継続的な努力こそがセンスを磨く鍵なのです。
将棋は奥深い世界であり、そのセンスを磨く道には終わりがありません。しかし、適切な方法で日々研鑽を積めば、誰でも自分だけの独自のセンスを開花させることができるでしょう。将棋センスとは、結局のところ「才能を開花させるもの」なのです。

