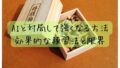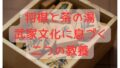将棋の道を歩む中で、必ず訪れる「中級者の壁」。基本的な戦術は身につけたものの、それ以上の進歩が見られず、勝率が伸び悩む時期です。多くの棋士がこの壁にぶつかり、中には将棋から離れてしまう人もいます。しかし、この壁を乗り越えることで、あなたの将棋はさらなる高みへと到達できるのです。本記事では、停滞期を抜け出し、次のステージへ進むための具体的な方法を、将棋の奥深さとともに解説していきます。
中級者の壁とは何か – その正体を解明する

将棋を指す人なら誰もが一度は経験する「中級者の壁」。なぜ成長が止まってしまうのでしょうか。まずはその正体を理解することから始めましょう。
中級者の壁とは、ある程度の基礎知識や技術を習得した後に訪れる成長の停滞期です。序盤の定跡は覚え、基本的な戦術も理解しているにもかかわらず、なかなか勝てなくなる時期です。この壁を突破するためには、まず自分の思考パターンや限界を客観的に把握する必要があります。
典型的な中級者の思考パターンと限界
中級レベルのプレーヤーは、序盤において駒の損得や玉の堅さを意識する傾向があります。しかし、中盤以降の戦いでは、駒の働きや手番(先手・後手)の重要性が増してきます。この変化に対応できず、序盤の思考パターンにとらわれていることが、成長の限界につながることがあります。特に終盤においては、駒の損得よりも速度、つまり手番が重視されるため、この意識の切り替えが重要になります。
思考時間も、中級者の成長を左右する要素の一つです。一般的に、思考時間が長いほど最適の一手に近づくと言えます。しかし、持ち時間が限られた対局においては、序盤や中盤で時間を使いすぎてしまい、終盤の重要な局面で十分な考慮時間が残らないというケースが見られます。いつ、どのくらい時間をかけるべきかという時間配分の戦略が、中級者にはまだ十分に身についていない可能性があります。
また、定跡(じょうせき:研究された基本の指し方)を覚えることは重要ですが、その表面的な手順だけを暗記し、意味を理解していない場合、応用力が利きません。独特な戦型や定跡を外れた局面に出くわした際に、どのように対応すれば良いか分からず、形勢を損ねてしまうことも少なくありません。
停滞感を感じる棋力帯の特徴
停滞感を感じやすい中級者の棋力帯には、いくつかの共通する特徴が見られます。まず、基本的な戦術、例えば両取りやピンなどは理解しており、簡単な詰め将棋も解けることが多いでしょう。得意な戦法を一つ持っていることも少なくありません。しかし、中盤から終盤への移行がスムーズにいかず、終盤の具体的な寄せの手順や戦略に苦労する傾向があります。
また、努力はしているものの、なかなか勝てないという「スランプ」のような状態に陥ることがあります。これは、自信の喪失や、自身の弱点を具体的に特定し、克服するための効果的な学習方法を見つけられていないことが原因かもしれません。
中級者の壁に関するプロ棋士の見解
プロ棋士は、中級者の壁を突破するために、まず終盤力の強化が不可欠であると考えています。将棋は最終的に相手の玉を詰ますゲームであり、終盤の強さが勝敗を大きく左右するためです。また、中盤から終盤にかけてのゲームの流れを理解し、相手の陣形を崩してから詰めろをかけるまでの一連の技術を習得することの重要性も指摘されています。
得意戦法を持つことは良いことですが、プロ棋士の中には、特定の戦法に固執しすぎることなく、幅広い戦型に対応できる柔軟性を持つことの重要性を説く人もいます。遭遇頻度の高い戦法を中心に、しっかりと対策を立てておくことが、中級から上級へとステップアップするために必要とされています。
「わかる」と「できる」のギャップを埋める
将棋のルールや戦法を「わかる」ことと、実際の対局で「できる」ことの間には、大きなギャップが存在します。多くの知識を頭で理解していても、それを対局というプレッシャーのかかる状況下で、適切なタイミングで引き出し、効果的に活用できなければ、棋力向上にはつながりません。
このギャップを埋めるためには、知識を習得するだけでなく、実戦を通して経験を積むことが不可欠です。自分の対局を振り返り、なぜその手が悪手だったのか、どうすればもっと良い手が指せたのかを分析することで、理解がより深いものになります。また、得意な分野を伸ばしつつ、苦手な分野にも積極的に取り組み、少しずつ克服していくというバランスの取れたアプローチも有効です。
自己診断 – あなたの停滞ポイントを特定する

停滞期を脱するためには、まず自身の弱点を正確に把握することが重要です。自分の何が足りないのか、どこに問題があるのかを理解することで、効率的に弱点を克服する道筋が見えてきます。
中級者に共通する7つの弱点タイプ
中級レベルのプレーヤーが陥りやすい弱点には、いくつかの共通するパターンがあります。
- 終盤力の不足: 終盤の寄せの手順や必至の概念が曖昧で、勝ちきれない、または逆転負けを喫してしまう。
- 序盤戦略の未熟さ: 特定の定跡に頼りすぎたり、序盤の駒組みの意図を理解していなかったりする。
- 中盤の戦略眼の欠如: 局面全体のバランスや有利不利の判断が曖昧で、効果的な攻めや受けの手を見つけられない。
- 読みの深さと正確性の不足: 複雑な局面で数手先まで正確に読むことができず、相手の攻めを見落としたり、自分の攻めが途中で頓挫したりする。
- 形勢判断の甘さ: 駒の損得だけでなく、玉の堅さ、駒の働き、手番といった要素を総合的に判断する力が不足している。
- 手筋の知識と応用の不足: 実戦で役立つ手筋を知らなかったり、知っていても適切な場面で活用できなかったりする。
- メンタルの弱さ: 対局中に集中力が途切れたり、プレッシャーに負けて実力を発揮できなかったり、連敗するとすぐに諦めてしまう。
これらの弱点タイプを踏まえ、自身の将棋を振り返ることで、停滞の根本原因が見えてくるはずです。
自分の対局から弱点を見つける分析法
自身の弱点を特定するためには、過去の対局を分析することが非常に有効です。対局の棋譜(きふ)を振り返り、自分がどのような局面でミスを犯しやすいのか、どのような状況で判断に迷うのかを客観的に見つめ直しましょう。
将棋ソフトのAI分析機能を利用することもおすすめです。AIは、局面ごとの評価値や推奨手を提示してくれるため、自分の指した手が最善手と比べてどうだったのか、どこで形勢を損ねたのかを具体的に把握することができます。特に、自分が「おかしいな」と感じた局面や、負けてしまった対局をAIで分析することで、見落としていた最善手や、致命的な悪手を発見できることがあります。
対局中、自分がどのような点に不安を感じたのか、どの手を選ぶべきか迷ったのかを記録しておくと、後で分析する際に役立ちます。また、負けが続く場合は、そのパターンを分析してみましょう。特定の戦法に対して勝率が低い、同じような戦術に引っかかってしまうなど、繰り返される負けパターンは、克服すべき明確な弱点を示唆しています。
棋風別の課題と克服法
棋風によって、陥りやすい課題も異なります。
- 攻め将棋: 常に攻めることばかりを考えてしまい、自玉の安全を疎かにしたり、受けの意識が低かったりする傾向があります。攻めるだけでなく、時には守り、相手の攻めを受け止める辛抱強さを養うことが重要です。
- 受け将棋: 守備に偏りすぎて、攻めるチャンスを逃したり、相手に主導権を握られやすい傾向があります。積極的に攻める意識を持ち、カウンターを狙うための手筋や判断力を磨く必要があります。
- 居飛車党: 振り飛車に対して、対策が偏っていると苦戦することがあります。様々な振り飛車戦法に対する知識を深め、臨機応変に対応できるようになることが求められます。
- 振り飛車党: 居飛車の急戦に対して、玉の囲いが間に合わなかったり、的確な受けの手を見つけられなかったりすることがあります。強固な囲いを築く手順を習得し、居飛車の攻めのパターンを理解しておくことが大切です。
具体的な棋力向上法 – 7つの実践ステップ

自分の弱点を把握したら、次はそれを克服するための具体的な方法に取り組みましょう。ここでは、中級者が次のレベルへステップアップするための7つの実践的なアプローチを紹介します。
1. 計画的な詰将棋トレーニング
詰将棋は、終盤力を鍛えるための最も効果的な方法の一つです。特に、寄せの技術や必至の概念を理解するのに役立ちます。単に数をこなすだけでなく、計画的に取り組むことが重要です。
初めは3手詰や5手詰などの短い詰将棋から始め、徐々に難易度を上げていくとよいでしょう。毎日少しずつでも継続的に解くことで、パターン認識能力が向上し、実戦でも似たような形を素早く見つけられるようになります。
また、詰将棋を解く際は、単に答えを見つけるだけでなく、なぜその手順が最短なのか、他の手だとなぜダメなのかを考えることで、思考力も鍛えられます。詰将棋の本やスマートフォンアプリなど、様々な教材が市販されていますので、自分のレベルに合ったものを選びましょう。
2. 実戦に即した定跡学習法
定跡を学ぶ際は、単に手順を暗記するのではなく、各手の意図や狙い、そして変化形に対する対応も含めて理解することが大切です。そうすることで、相手が定跡から外れた手を指した場合でも、柔軟に対応できるようになります。
まずは自分の得意戦法に関連する定跡を深く学ぶことから始めましょう。戦型ごとの基本的な考え方や目指すべき形、注意すべきポイントなどを理解することで、実戦での判断力が養われます。
プロ棋士の解説本や講座、インターネット上の解説動画なども参考になります。特に、なぜその手を選んだのか、どのような狙いがあるのかという解説を重視して学びましょう。実戦で同じような局面に出会ったとき、その知識が活きてきます。
3. 中盤の戦略眼を鍛える実践法
中盤の戦略眼を鍛えるためには、局面の大局観を養うことが重要です。これには、プロ棋士の対局を解説付きで観戦したり、名局の棋譜を並べたりすることが効果的です。プロがどのような判断基準で手を選んでいるのか、どのような戦略で相手に挑んでいるのかを学ぶことで、自分の判断力も向上します。
また、一つの局面から複数の候補手を考え、それぞれがどのような展開につながるかを想像する練習も有効です。「この手を指すと相手はどう応じるか」「その後の局面はどうなるか」といった思考実験を繰り返すことで、先を読む力が養われます。
実戦で負けた局面を振り返る際は、「どの時点で形勢が悪化したのか」「どんな手を指せばよかったのか」を具体的に分析しましょう。将棋ソフトの評価値を参考にしつつ、自分の思考プロセスを見直すことで、判断力の向上につながります。
4. 読みの精度を高めるトレーニング
読みの精度を高めるためには、実戦形式の問題集や、詰め将棋より複雑な「次の一手」問題に取り組むことが効果的です。これらの問題では、単に「詰む」「詰まない」だけでなく、「最善手は何か」を考える必要があります。
読みを深める際は、自分の思考を言語化する習慣をつけると良いでしょう。「この手を指すと相手はこう応じる」「その後こちらはこう指す」というように、一手ずつ明確に言葉にしながら読むことで、思考が整理され、抜け漏れが減ります。
また、実戦で難しい局面に遭遇したら、その局面を記録しておき、後で時間をかけて読み直す練習も有効です。時間制限のない環境で正確に読む訓練を積むことで、実戦での読みの精度も向上していきます。
5. 形勢判断力を磨く方法
形勢判断力を磨くためには、プロ棋士の解説や将棋ソフトの評価値を参考にしながら、様々な局面での勝敗の分かれ目を学ぶことが大切です。特に、駒の損得だけでなく、玉の安全性、駒の働き、手番の価値などを総合的に評価する視点を養いましょう。
実戦の棋譜を並べる際に、「この局面は先手有利か後手有利か」「どのくらい有利か」を自分で判断してから、将棋ソフトの評価と比較する練習も効果的です。最初は評価がずれることが多いかもしれませんが、繰り返すうちに徐々に精度が上がっていきます。
また、プロ棋士の棋譜解説や、対局での形勢判断に関するコメントを注意深く読むことで、形勢判断のヒントが得られます。「なぜこの局面で優勢と判断したのか」「何を重視して評価したのか」という視点を学ぶことが大切です。
6. 手筋の活用力を高める学習法
手筋を効果的に学ぶためには、単に知識として覚えるだけでなく、実戦で活用できるようになることが重要です。手筋の解説書や問題集に取り組み、代表的な手筋のパターンを頭に入れましょう。
特に重要なのは、手筋が有効な条件や状況を理解することです。「この手筋はどんな局面で使えるのか」「使う際の注意点は何か」といった点を押さえておくと、実戦での応用力が高まります。
また、自分の対局で使った手筋や、使い損ねた手筋を記録しておき、定期的に復習することも効果的です。実践と理論を結びつけることで、手筋の活用力が自然と身についていきます。
7. メンタル強化のためのルーティン確立
将棋は精神的な側面も非常に重要です。プレッシャーに負けない強いメンタルを養うには、対局前のルーティンを確立し、心身の状態を整えることが有効です。
例えば、対局前に軽い運動や深呼吸を行う、前日は十分な睡眠をとる、栄養バランスの良い食事を心がけるなど、基本的な体調管理も重要です。また、過去の勝負を引きずらず、一局一局に集中する心構えも大切です。
連敗した場合も、必要以上に落ち込まず、「何が原因だったのか」を冷静に分析する習慣をつけましょう。負けから学ぶ姿勢があれば、一時的な停滞も成長のチャンスに変えることができます。
効率的な学習リソースの活用法

将棋の上達には、質の高い学習リソースを効率的に活用することが欠かせません。ここでは、中級者におすすめの書籍やウェブサイト、アプリなどを紹介し、それらを最大限に活用するためのヒントをお伝えします。
おすすめの棋書と活用法
中級者におすすめの棋書には、以下のようなものがあります。
- 終盤力を鍛える本: 詰将棋や寄せの手筋に関する書籍は、終盤力向上に直結します。難易度に応じて選び、少しずつレベルアップしていきましょう。
- 戦型別の解説書: 自分の得意戦法や苦手な相手戦法に関する解説書は、戦略的な理解を深めるのに役立ちます。
- プロ棋士の対局集: 名局の解説付き棋譜は、大局観や戦略眼を養う上で貴重な教材です。
棋書を読む際は、ただ眺めるだけでなく、実際に盤面を並べながら手を追うことで理解が深まります。また、わからない部分があれば放置せず、将棋ソフトで確認したり、将棋教室で質問したりすることも大切です。
オンライン将棋サイトの効果的な使い方
ネット将棋は、時間や場所を選ばずに対局できる便利なツールです。ただし、単に多くの対局をこなすだけでは上達は限られます。効果的な活用法としては、以下のポイントを意識しましょう。
- 対局後の振り返り: 勝敗にかかわらず、対局後は必ず棋譜を見直し、良かった点、改善すべき点を分析します。
- テーマを設定した対局: 例えば「今日は相居飛車で戦う」「終盤の寄せを意識する」など、特定の目標を持って対局することで、弱点の克服につながります。
- 強豪プレイヤーの観戦: 自分より強いプレイヤーの対局を観戦し、その指し方や考え方を学ぶことも有効です。
また、多くのオンライン将棋サイトでは棋譜の保存機能があります。これを活用して、自分の成長記録として残しておくとよいでしょう。
AIと将棋ソフトの賢い活用術
将棋AIやソフトは、適切に活用すれば強力な学習ツールとなります。
- 棋譜解析: 自分の対局をAIで解析し、悪手や好手を客観的に評価してもらうことで、盲点に気づくことができます。
- 形勢判断の学習: AIの評価値と自分の感覚を比較することで、形勢判断力が養われます。
- 次の一手問題: AIを使って様々な局面から「次の最善手は何か」を考える練習も効果的です。
ただし、AIの評価や推奨手をただ鵜呑みにするのではなく、「なぜその手が良いのか」を自分なりに考察することが大切です。AIは強力なサポートツールですが、最終的な判断は自分自身で行う力を養いましょう。
停滞期からのブレイクスルー事例

実際に中級者の壁を乗り越え、次のレベルへと進んだ棋士たちの体験談は、大きな励みになります。ここでは、様々なタイプの停滞から抜け出した実例を紹介し、その成功のポイントを分析します。
終盤力の向上でレベルアップした例
Aさんは、中盤までは良い将棋を指せるものの、終盤で勝ちきれないという悩みを抱えていました。詰将棋を毎日10問解く習慣をつけ、特に実戦的な詰め将棋や、寄せの手筋を集中的に学習しました。また、実戦で勝てなかった局面を取り出し、「どうすれば勝てたか」を詰め将棋の視点から分析する習慣もつけました。
3ヶ月後、Aさんは終盤の局面での判断力が向上し、それまで逃していた勝機を確実に勝ちに結びつけられるようになりました。形勢が優勢な局面では、攻めの手筋を的確に使い、必至の形を作れるようになったことが、レベルアップの大きな要因となりました。
定跡理解の深化で戦型対応力を高めた例
Bさんは、得意な戦法では勝てるものの、苦手な戦型に出会うと途端に力を発揮できないという弱点がありました。そこで、特に苦手としていた相振り飛車戦について、定跡書を徹底的に学び、その背後にある考え方や狙いを理解することに努めました。
単に手順を覚えるだけでなく、「なぜこの手が選ばれるのか」「この形で何を目指すのか」という観点から学習を進めたことで、定跡から外れた局面でも適切な判断ができるようになりました。その結果、以前は苦手としていた戦型でも安定した成績を残せるようになり、総合的な棋力アップにつながりました。
集中力と時間管理の改善で実力発揮した例
Cさんは、技術的には一定のレベルに達していたものの、対局中の集中力維持と時間管理に問題を抱えていました。長考による時間切れや、終盤での焦りによる凡ミスが多く、実力を発揮できない状況が続いていました。
そこでCさんは、対局前のルーティンを確立し、精神的な安定を図るとともに、時間配分を意識した練習を重ねました。例えば、序盤は比較的早く指し、中盤の戦略的判断や終盤の詰めの局面に時間を残すよう意識するなど、具体的な時間管理の戦略を立てました。
こうした取り組みにより、Cさんは時間切れによる敗戦が減少し、終盤まで冷静に判断できるようになりました。特に長時間対局での勝率が向上し、トーナメント形式の大会でも好成績を残せるようになりました。
まとめ

将棋における「中級者の壁」は、誰もが経験する成長過程の一部です。停滞期を乗り越えるためには、まず自分の弱点を正確に把握し、それを克服するための具体的な学習計画を立てることが重要です。
終盤力の強化、定跡の深い理解、中盤の戦略眼の養成、読みの精度向上、形勢判断力の向上、手筋の活用力強化、そしてメンタル面の強化。これらの要素をバランスよく鍛えることで、着実にレベルアップを果たすことができます。
また、質の高い学習リソースを効果的に活用し、計画的かつ継続的に取り組むことも大切です。将棋ソフトやAIも、使い方次第で強力な学習ツールとなります。
最後に、将棋の上達には時間がかかります。一時的な停滞に落ち込むのではなく、それを成長のチャンスと捉え、粘り強く取り組む姿勢が大切です。短期的な勝敗にとらわれず、長期的な視点で自分の将棋を見つめ直し、一歩一歩確実に前進していきましょう。
あなたの将棋が、この記事をきっかけに新たな段階へと進化することを願っています。